
虫歯の原因は「細菌」です。
プラーク内に潜む細菌が酸を出すことで歯が溶かされていき、しみる・痛むという症状が出てきます。
一方で、虫歯が神経近くにまで進行しない限り、しみや痛みを感じることはありませんので、ご自身で「虫歯かもしれない」と思ったときには想像以上に虫歯が進行している状態です。
だからこそ早く治療する必要があるのですが、治療が本質ではなく「再発させないためのアプローチ」がとても重要であると言えます。
患者様に寄り添いながら、虫歯治療を行います。

繰り返しになりますが、虫歯は「細菌による病気である」ということです。精度の高い治療を行っても原因をご理解いただけなければ、虫歯は再発してしまいます。
つまり、どうして虫歯になるのかがわからなければ再発を繰り返し、結果的に歯を失ってしまうことに繋がってしまうのです。
だからこそ、患者様に虫歯という病気への理解を促し、徹底したメンテナンスによる再発防止を促さなければ、身体的にも経済的にも負担がかかってしまいます。
当院では、患者様に丁寧な説明を通して虫歯という病気を知っていただき、ご自身の歯を一緒に守っていくように働きかけます。
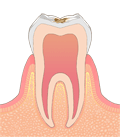
気づきにくいですが、この状態であれば麻酔をする必要がなく、場合によってはクリーニングとフッ素と定期検診を行えば元の状態に戻せる可能性があります。
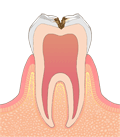
虫歯がエナメル質を超えて象牙質にまで達した状態です。歯髄にまで近づくことでしみたり痛みを感じることが多くなります。

歯の神経付近もしくは神経にまで虫歯が進行している状態です。神経を残せるかどうかを判断しなければならず、神経にまで到達し壊死している場合は、抜髄治療(根管治療)が必要になります。
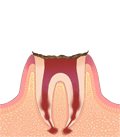
神経が壊死し、歯根にまで虫歯が進行した状態です。これを感染根管と言います。感染根管治療を行い、歯が保存できるかどうかを判断する必要があります。最悪の場合、抜歯になるケースもあります。

どの治療を行うにも検査というのは重要でありますが、大切なのは「なぜ虫歯になってしまったのか?」という原因を発見することが大切です。
口腔内を見るだけにとどまらず、ヒアリングを行い詳しく背景をお聞きすることで、治療後の虫歯予防の計画にも役立ちます。

治療の痛みが一番歯医者を疎遠にしてしまっている部分ではないかと思います。当院では痛みを感じにくいように配慮した麻酔と治療を行います。
患者様の治療に掛かる負担を軽減させることを大切にしています。

歯の神経は、歯の強度を保つために重要な役割を持っています。
神経を失った歯は失活歯と呼ばれ、歯の栄養である血液が行き渡らず、歯が欠けやすく割れやすい状態になってしまいます。だからこそ、残せるのであれば神経を残すことを第一に考えた治療を行います。
治療の精度を高めるために、拡大鏡やマイクロスコープを用いた精密かつ丁寧な治療を行います。

虫歯は再発させないことが何よりも重要です。そのためには治療後の定期メンテナンスを徹底することが大切です。
患者様にも日常的なブラッシングをご協力いただきますが、日々どれだけ完璧にブラッシングをしたとしてもご自身でプラークが残存しているかは判断が付きません。
そのために定期的にいらしていただき、メンテナンスを行うことで虫歯の再発に努めていきます。治療を繰り返すよりも定期メンテナンスを行うほうが経済的な負担も軽くなります。
まず問診及び視診を行います。
患者様からお話を伺い、生活習慣等背景を教えていただきながら原因を探ります。
その後お口の中を視診し、虫歯の進行度合いを見ていきます。
パノラマレントゲンの撮影をします。お口全体の状況を把握するために必要になります。必要に応じて1歯を撮影するデンタルレントゲンで撮影することもあります。
主訴の改善を行います。痛みがお有りになられる場合は、痛みを取り除き応急処置を完了させます。レントゲンなどを見て診査・診断をする必要がありますので、初診時はこの段階で一度帰宅いただきます。
診断結果のご説明を行います。このときに虫歯になってしまった原因、現状の進行度合い、治療計画のご説明を行います。
虫歯の進行度合いによって治療内容は変わりますが、う蝕検知液を使用しながら丁寧に虫歯を取り除いていきます。大切なのは虫歯を取り残さないこと。虫歯を取り残してしまうと、取り残した虫歯が進行していくことになります。最終的にコンポジットレジン充填・インレー・アンレー・クラウンといった治療部を補って治療が完了となります。、
定期的に通院していただき、お口の中を清掃していきます。このときに歯科衛生士より磨き残しがある部分、磨きにくい部分などをお伝えし、日々のブラッシングの質を高めていただきます。

むし歯は、早い段階で発見する事が大切です。
なるべく早い段階で発見することが出来れば、大きく・深く削ること無く、ご自身の健康な歯を守ることが出来ます。
しかし、深い虫歯や神経に穴が空いてしまっている場合は、大きな痛みを伴うことがあります。そのような場合でも、神経をなるべく取らない様にと、当院は考えます。
神経を取ることは、虫歯治療の中でも最後の段階です。だからこそ、早めに受診をしてむし歯を解決することが重要です。
そして何よりメンテナンスを行い、再発予防に努めていただくことが虫歯治療で最も重要であると言っても過言では有りません。
当院では患者様に寄り添い、治療後の良好な状態が維持できるよう最大限努力致します。
虫歯でお困りになられたらお気兼ねなくご相談ください。きっとお役にたてるはずです。